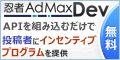剛蔵の空想履歴、創作小説の部屋へようこそ!!リンクはフリーです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2、8月6日。晴れ時々雨…。
君とはあれから何度か逢って話をした。といっても、パターンは同じだ。
僕が歌う、彼女がくる、歌い終わる、話す…の繰り返し。
僕が路上へ出るのは週2日。
そのうち、金曜の午後は彼女を待ち、歌うことが多くなった。
今日も彼女を待っていたんだけれど、ついに夕暮れ時まで現れなかった。
仕方がないので、僕は渋々、歌を歌いはじめた。
君が来ないことでやる気は半減。
何曲歌ったか忘れてしまったころ…
目の前に黒いスーツ姿・年齢にして40後半くらいの真面目そうな男が立った。
僕を見て、近くへ寄ってくる。真剣な顔つきをしていた。
いつもからんでくる酔っ払いではないことは明らかだった。
「雄二くん…だね?」
「あ、はい…そうですけど…何か?…」
僕は怖かった…今までの路上活動では向けられたことのない
暖かくもあり悲しくもあるその目に僕は吸い寄せられていた。
「樋口利雄、早苗の父です。はじめまして」
「あ、どうも…はじめまして…」
「最近、早苗が良く君の歌を聞きに行くのだと
嬉しそうに話していてね、今日は私が来てみた。」
「ああ、そうでしたか、ありがとうございます。」
なんだかそれ以上の言葉が出てこなかった。
彼女だけでなく、親子でなく、父だけが今日、僕の目の前に。
そんな優し悲しい顔をして立っているのか。
僕は怖くて聞けなかった。目も合わせられなかった。
「ちょっと向こうで座って話せるかな?」
‘早苗のお父さん’は以前のスポットに近い、公園のベンチを指して言った。
「ええ、いいですよ、そろそろ休憩しようと思っていたので」
僕は平然を装ってそう答えた。
ベンチに座ってすぐに話は本題に入った。
僕の運命がカラカラと音を立て
僕の想像できないスピードで早まっていくのを感じた。
「早苗は今、入院している…。」
「え?」
あんなに綺麗で優しい彼女が入院…?訳が分からなかった。
こんなに暑いのに長袖なのか?と聞いても
「肌が弱いから、日焼け対策なの」とただ笑っていた。
そこらへんを歩く子となんら違いは感じなかった。
感じさせなかったのか?そうなのか?
僕は訳がわからない顔で‘早苗のお父さん’を見上げた。
「あの子について、少し話してもいいかな?」
「はい、お願いします…」
「あの子は生まれつき、心臓が弱くてね…。
でも小学校の頃までは、ほかの子変わらす学校に行っていたんだ。
でもある日、音楽の授業で歌を歌っていてね。
そこで歌の途中で苦しくなって倒れた。
それ以来、あの子は歌を怖がった。鼻歌を口ずさむこともなくなった。
あの子は歌が大好きだったのに、その歌が歌えないことで
心を徐々に閉ざしていった。口数も少なくなっていったんだ。」
「でも…、でも、あんなに元気に明るく、ここにきてたじゃないですか」
「君にはとても感謝している。あの子は高校に行っていなくてね。
私が行かせなかったんだ。
これ以上、あの子から歌以外のものまで奪ってしまうのではないかと思ってね。
でもそれは逆効果だった。
あの子は友達も出来ず、外にでることも諦めてしまった。
病状は安定したよ。でもそれでは生きているといえるのか?
私は答えが出せないでいた。
でもある時から、早苗は変わり始めた。
君が窓の外で、この公園の街灯の下で歌うようになってからだ。」
指を指した先には、こげ茶色の瓦の家が一件見えた。あそこが彼女の家らしい。
「夜になると早苗はいつもあの部屋のベランダで君を見ていた。
あの距離だ、歌はちゃんと聞こえなかっただろうけど
そのギターの音くらいはしっかり聞けたんじゃないかな?
実際、今日聞いて思ったよ、いい音をしている。
私も昔、ちょっと弾いていたことがあってね。
よく早苗と一緒に歌った。多分、それを覚えていたんだろう」
お爺のギターは偉大だった。
僕は感謝半分、嫉妬半分に重く閉ざした口をリハビリでもするかのごとく
ゆっくりと開いて話した。
「じいちゃんの使ってたギターなんです。
いつ作られたか、とか知らないんですけど
この音が彼女に元気を与えていたのなら
じいちゃんに感謝しないといけないですね」
「いや、そのギターだけじゃないんだ、早苗が元気になったのは。
一番効いたのは君の歌だよ。
早苗はしばらくすると、君のギターに合わせて鼻歌を歌うようになった。
あの早苗が、あの子が歌を歌っている…。
それだけで奇跡を見た気分だった。
でもそれだけで止まらなかった。
あの子は自分から外へ出たいと言った。そして君に会いにいった。」
そうか…あの日、あの場所だったから、彼女は僕に近づけた。
そして僕は君に忘れられない歌を、一夜をプレゼントしたんだ。
意図せず僕はそうして、君は意図してそうしたのか?自分の身体に鞭打って…。
「今、どうしてるんですか?彼女は…。助かるんですか?」
聞くことは怖かった…けど、聞かずにはいられなかった…。
ほんの数秒だったけど、僕はいいシュミレーションを何度も何度も繰り返した…。
「今は安静にしていれば大丈夫…。でも先はわからない。
心臓の筋力が生まれつき弱くてね。
体が大きくなるにつれて年齢を重ねるにつれて、心臓に負担が掛かっていく。
そういう病気だから…覚悟はしているつもり…なんだ…。」
「そうですか…、今日……いえ……明日…会えますか?」
出来れば今日、今すぐに会いにいきたかった。
正直、彼女と出会ってからの路上活動は今までになく力強く、優しく
希望に溢れたものだったから…。
もう彼女なしでは僕の歌は存在し得ない。
僕の歌は彼女の為に…そう…早苗の為にあることを今、確信した。
「来てくれるか……早苗も喜ぶよ。」
かすれた声だった。嬉しさと悲しさを胸一杯に込め、それを押さえつけた声だ。
「じゃあ、明日、午後に『はじめ総合病院』302号室、来てくれるかな?」
「はい、わかりました、必ず行きます」
「じゃあ、また明日。」
後姿を見送って、僕は太陽の光を全身に受けた月を見上げた…。
大きく手が届きそうな月…。
君と見た月が大きくその口を開けて
僕だけでなく君の魂やすべてを飲み込んでしまいそうで怖かった。
明日…君に会って話そう…これからのこと、未来のこと。一杯話そう…。
小粒の雨が降り始めたのは、それからかなりの時間が経ってからだ。
僕は歌うことも出来ず、帰ることも出来ず、空を見上げていた。
月はいつしか雲に覆われていた。
真夏の夜を…火照った真夏の夜の行き場のない感覚を
冷ますかのように…しとしとと…つらつらと降る雨。
あの日、どうやって家まで帰ったのかは記憶していないんだ。
あの日の雨は覚えているのに…。
君とはあれから何度か逢って話をした。といっても、パターンは同じだ。
僕が歌う、彼女がくる、歌い終わる、話す…の繰り返し。
僕が路上へ出るのは週2日。
そのうち、金曜の午後は彼女を待ち、歌うことが多くなった。
今日も彼女を待っていたんだけれど、ついに夕暮れ時まで現れなかった。
仕方がないので、僕は渋々、歌を歌いはじめた。
君が来ないことでやる気は半減。
何曲歌ったか忘れてしまったころ…
目の前に黒いスーツ姿・年齢にして40後半くらいの真面目そうな男が立った。
僕を見て、近くへ寄ってくる。真剣な顔つきをしていた。
いつもからんでくる酔っ払いではないことは明らかだった。
「雄二くん…だね?」
「あ、はい…そうですけど…何か?…」
僕は怖かった…今までの路上活動では向けられたことのない
暖かくもあり悲しくもあるその目に僕は吸い寄せられていた。
「樋口利雄、早苗の父です。はじめまして」
「あ、どうも…はじめまして…」
「最近、早苗が良く君の歌を聞きに行くのだと
嬉しそうに話していてね、今日は私が来てみた。」
「ああ、そうでしたか、ありがとうございます。」
なんだかそれ以上の言葉が出てこなかった。
彼女だけでなく、親子でなく、父だけが今日、僕の目の前に。
そんな優し悲しい顔をして立っているのか。
僕は怖くて聞けなかった。目も合わせられなかった。
「ちょっと向こうで座って話せるかな?」
‘早苗のお父さん’は以前のスポットに近い、公園のベンチを指して言った。
「ええ、いいですよ、そろそろ休憩しようと思っていたので」
僕は平然を装ってそう答えた。
ベンチに座ってすぐに話は本題に入った。
僕の運命がカラカラと音を立て
僕の想像できないスピードで早まっていくのを感じた。
「早苗は今、入院している…。」
「え?」
あんなに綺麗で優しい彼女が入院…?訳が分からなかった。
こんなに暑いのに長袖なのか?と聞いても
「肌が弱いから、日焼け対策なの」とただ笑っていた。
そこらへんを歩く子となんら違いは感じなかった。
感じさせなかったのか?そうなのか?
僕は訳がわからない顔で‘早苗のお父さん’を見上げた。
「あの子について、少し話してもいいかな?」
「はい、お願いします…」
「あの子は生まれつき、心臓が弱くてね…。
でも小学校の頃までは、ほかの子変わらす学校に行っていたんだ。
でもある日、音楽の授業で歌を歌っていてね。
そこで歌の途中で苦しくなって倒れた。
それ以来、あの子は歌を怖がった。鼻歌を口ずさむこともなくなった。
あの子は歌が大好きだったのに、その歌が歌えないことで
心を徐々に閉ざしていった。口数も少なくなっていったんだ。」
「でも…、でも、あんなに元気に明るく、ここにきてたじゃないですか」
「君にはとても感謝している。あの子は高校に行っていなくてね。
私が行かせなかったんだ。
これ以上、あの子から歌以外のものまで奪ってしまうのではないかと思ってね。
でもそれは逆効果だった。
あの子は友達も出来ず、外にでることも諦めてしまった。
病状は安定したよ。でもそれでは生きているといえるのか?
私は答えが出せないでいた。
でもある時から、早苗は変わり始めた。
君が窓の外で、この公園の街灯の下で歌うようになってからだ。」
指を指した先には、こげ茶色の瓦の家が一件見えた。あそこが彼女の家らしい。
「夜になると早苗はいつもあの部屋のベランダで君を見ていた。
あの距離だ、歌はちゃんと聞こえなかっただろうけど
そのギターの音くらいはしっかり聞けたんじゃないかな?
実際、今日聞いて思ったよ、いい音をしている。
私も昔、ちょっと弾いていたことがあってね。
よく早苗と一緒に歌った。多分、それを覚えていたんだろう」
お爺のギターは偉大だった。
僕は感謝半分、嫉妬半分に重く閉ざした口をリハビリでもするかのごとく
ゆっくりと開いて話した。
「じいちゃんの使ってたギターなんです。
いつ作られたか、とか知らないんですけど
この音が彼女に元気を与えていたのなら
じいちゃんに感謝しないといけないですね」
「いや、そのギターだけじゃないんだ、早苗が元気になったのは。
一番効いたのは君の歌だよ。
早苗はしばらくすると、君のギターに合わせて鼻歌を歌うようになった。
あの早苗が、あの子が歌を歌っている…。
それだけで奇跡を見た気分だった。
でもそれだけで止まらなかった。
あの子は自分から外へ出たいと言った。そして君に会いにいった。」
そうか…あの日、あの場所だったから、彼女は僕に近づけた。
そして僕は君に忘れられない歌を、一夜をプレゼントしたんだ。
意図せず僕はそうして、君は意図してそうしたのか?自分の身体に鞭打って…。
「今、どうしてるんですか?彼女は…。助かるんですか?」
聞くことは怖かった…けど、聞かずにはいられなかった…。
ほんの数秒だったけど、僕はいいシュミレーションを何度も何度も繰り返した…。
「今は安静にしていれば大丈夫…。でも先はわからない。
心臓の筋力が生まれつき弱くてね。
体が大きくなるにつれて年齢を重ねるにつれて、心臓に負担が掛かっていく。
そういう病気だから…覚悟はしているつもり…なんだ…。」
「そうですか…、今日……いえ……明日…会えますか?」
出来れば今日、今すぐに会いにいきたかった。
正直、彼女と出会ってからの路上活動は今までになく力強く、優しく
希望に溢れたものだったから…。
もう彼女なしでは僕の歌は存在し得ない。
僕の歌は彼女の為に…そう…早苗の為にあることを今、確信した。
「来てくれるか……早苗も喜ぶよ。」
かすれた声だった。嬉しさと悲しさを胸一杯に込め、それを押さえつけた声だ。
「じゃあ、明日、午後に『はじめ総合病院』302号室、来てくれるかな?」
「はい、わかりました、必ず行きます」
「じゃあ、また明日。」
後姿を見送って、僕は太陽の光を全身に受けた月を見上げた…。
大きく手が届きそうな月…。
君と見た月が大きくその口を開けて
僕だけでなく君の魂やすべてを飲み込んでしまいそうで怖かった。
明日…君に会って話そう…これからのこと、未来のこと。一杯話そう…。
小粒の雨が降り始めたのは、それからかなりの時間が経ってからだ。
僕は歌うことも出来ず、帰ることも出来ず、空を見上げていた。
月はいつしか雲に覆われていた。
真夏の夜を…火照った真夏の夜の行き場のない感覚を
冷ますかのように…しとしとと…つらつらと降る雨。
あの日、どうやって家まで帰ったのかは記憶していないんだ。
あの日の雨は覚えているのに…。
PR
この記事にコメントする